目次
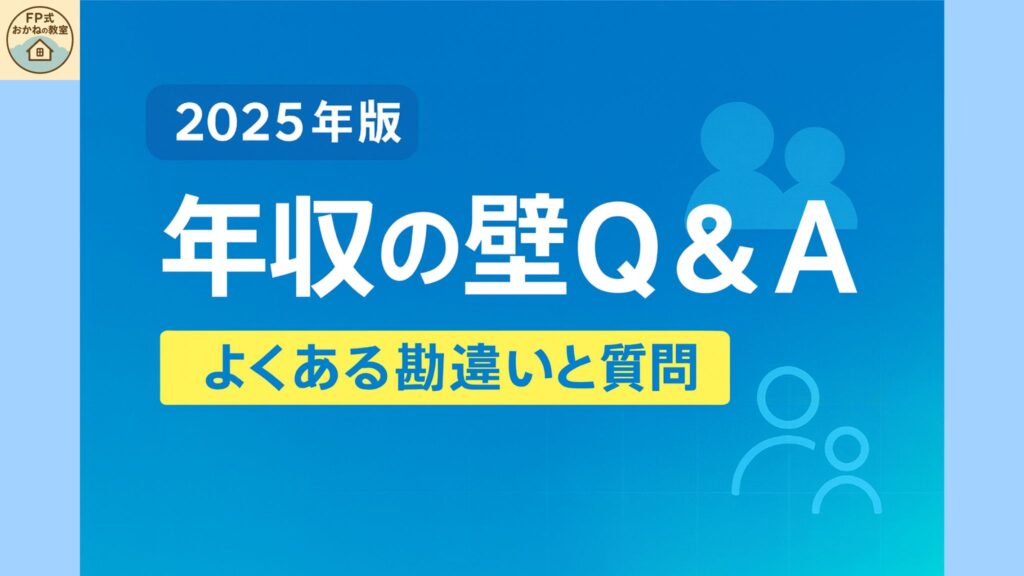
収入の壁Q&A集(2025年版)
※本Q&Aは学習用の一般例です。住民税は自治体差、社会保険は加入先の基準や標準報酬等で金額・判定が変わります。最終確認は勤務先(人事・健保)・自治体・税務署の公式情報で行ってください。
110万円(住民税)の壁
- 誤解:100万円で必ず課税。
- 正解:単身・給与のみの一般例では、年収110万円以下は所得割が非課税の目安です。
- ポイント:均等割は自治体ごとに基準が異なるため、110万円でも数千円課税の場合あり。
翌年度の住民税です(例:2025年の収入→2026年度の住民税)。
通勤手当には非課税枠があります。会社の支給方法によって課税・非課税の扱いが違うため、会社の規程で確認してください。
123万円(所得税)の壁
あなた本人の所得税の非課税ラインです。
基礎控除58万円+給与所得控除65万円=123万円。
勤労学生控除で非課税目安が上がる場合があります。条件や他の所得で変わるため、学校・税務署の案内も確認を。
判定は年収ベース。超えた部分にだけ所得税がかかります(崖ではなく段階課税)。
130万円(社会保険の「被扶養」)
一般には被扶養=本人保険料なしですが、週20時間などの加入要件に該当すると130万円未満でも加入になる場合があります。
見込み年収で判定します。一時的超過は事業主の証明があれば継続扱いの特例あり(健保の案内を確認)。
被扶養の130万円判定は合算します。一方、週20時間などの加入要件は会社ごとに判定(合算しない)です。
106万円(社会保険の「加入要件」:撤廃へ移行中)
別モノです。106万=加入要件、130万=被扶養判定。106に当たる人は130未満でも加入になります。
賃金要件を撤廃し、段階的に企業規模要件も縮小・撤廃へ。今後は週20時間など「時間」基準が中核に。
150万/160万円(配偶者(特別)控除)
配偶者(特別)控除の満額ゾーンの話です。2025年改正で満額が160万円までに。以降は約201.6万円まで段階縮小(急にゼロではない)。
主たる納税者に所得制限があります。年収帯により縮小〜適用なしの可能性。
別の制度です。123万=本人の所得税、150/160万=配偶者側の控除の話。
実務でよく迷うポイント
多くは段階的(逓減)です。崖になるのは被扶養の可否など一部。数字で試算を。
短期の手取りは増でも、将来の年金・給付が薄くなる場合あり。今 vs 将来のトレードオフで判断。
原則年収(見込み)に入れます。通勤手当は非課税枠の扱いに注意/賞与・残業は当然カウント。
今後の見込み年収が基準未満なら被扶養へ戻る可能性。手続きは健保・会社で確認。
会社ごとに判定(合算しない)。ただし被扶養の130万円は収入合算。ここを混同しないこと。
時限・要件付きです。通常は58万円。適用年度・要件は最新情報で要確認。
◀前 【年収ライン別手取り早見表&シミュレーション】 へ戻る






