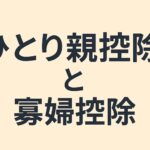目次

ひとり親家庭が利用できる制度の中には、申請するだけで毎月数万円支給されるものもあります。 ですが、それを知らなかったり、所得の目安を勘違いしていることで、損をしてしまう人も…。 この記事では、主な制度の内容・支給額・申請条件をわかりやすくまとめました。
📌児童扶養手当(1人目〜2人目以降まで)
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活安定と自立支援を目的に、**18歳までの子ども(高校卒業まで)**を扶養している親に支給される手当です。
(障害がある場合は20歳まで)。
所得制限と支給額(2025年度版)
所得が一定額以下であれば全額支給、それを超えても一部支給される仕組みです。支給額は以下の通りです。
| 対象児童 | 全額支給(月額) | 一部支給(月額) |
|---|---|---|
| 第1子 | 44,140円 | 10,410円〜44,130円 |
| 第2子 | +10,420円 | 5,210円〜10,410円 |
| 第3子以降 | +6,250円/人 | 3,130円〜6,240円 |
所得制限ラインの目安(本人所得ベース)
| 扶養人数 | 全額支給の上限所得 | 一部支給の上限所得 |
|---|---|---|
| 扶養0人 | 490,000円以下 | ~1,920,000円程度 |
| 扶養1人 | ~1,870,000円以下 | ~2,300,000円程度 |
| 扶養2人 | ~2,300,000円以下 | ~2,600,000円程度 |
※所得とは「収入(給料」ではないので注意してください 年収=所得✖
▼所得と収入の違いはコチラの記事で解説しています。
一部支給と全額支給の違い
所得制限を超えると段階的に減額されていきます。支給額が1円でも出れば「一部支給」となりますが、年収や扶養人数に応じて細かく計算されます。
補足:証書の役割
児童扶養手当を受け取っていると、「児童扶養手当証書」が交付されます。これは自治体の支援制度(保育料減免、医療費助成など)を申請する際に証明書類として使えることがあります。
📌ひとり親控除(所得税・住民税)
ひとり親控除は、所得税・住民税を軽減するための制度です。2021年から制度が見直され、「寡婦控除」に代わる形で導入されました。
控除額と条件(令和6年以降)
| 税目 | 控除額 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 所得税 | 35万円 | 扶養している子がいる(未婚・離婚・死別いずれも対象) |
| 住民税 | 30万円 | 同上 |
✅ 所得500万円以上は対象外(合計所得金額基準)
✅ 「子と生計を一にしていること」が条件です
再婚・パートナーがいるとどうなる?
- 婚姻関係(再婚)した場合:対象外
- 事実婚(同居のパートナーがいる):対象外とされるケース多数(自治体判断)
➡ よって「一人で子どもを育てている」ことが明確な状況でなければ、適用されない場合があります。
寡婦控除との違い(簡潔比較)
| 項目 | 寡婦控除 | ひとり親控除 |
|---|---|---|
| 対象 | 配偶者と死別・離婚(子なしでもOK) | 子どもを扶養している親(男女問わず) |
| 性別 | 女性のみ | 男女問わず |
| 控除額 | 27万円(所得税) | 35万円(所得税) |
| 特例あり | 寡婦特例で35万円控除あり | — |
🔍 補足:「寡婦控除」は、今も残っていますが「子どもがいない女性のみ対象」など限定的です。
▼ひとり親控除・寡婦控除の詳細はコチラで解説しています。
📌住民税非課税・国保の減免制度
住民税非課税の条件(令和6年度)
住民税の非課税となる目安は、所得が45万円以下+扶養控除などです。児童扶養手当を受給していれば、住民税が非課税となる可能性が高いです。
✅ 非課税だと以下のメリットが:
- 国民健康保険料が大幅減免
- 保育料が無料または減額
- 高校授業料の無償化対象に
- 各種給付金(例:臨時特別給付金)の支給対象になる可能性
国保減免制度の仕組み
多くの自治体では、児童扶養手当の受給証書を提出することで、自動的に国保の減免申請が可能です(または簡易な書類提出のみ)。
支払い能力に応じて、所得割・均等割が減額される仕組みです。
住民税が自動で非課税になる人/申請が必要な人
住民税の「非課税世帯」として認定されるかどうかは、所得・家族構成・扶養人数などによって決まります。
自治体によって細かい違いはありますが、基本的な仕組みは以下の通りです。
● 自動で非課税になるケース
住民税は、毎年1月1日時点の住所地の自治体が、前年の所得をもとに自動計算します。
そのため、次のような人は、申請をしなくても非課税世帯として扱われます。
| 自動で非課税になる主なケース |
|---|
| ・前年の所得が「非課税基準以下」の人(例:所得45万円以下+扶養あり) |
| ・前年に「確定申告」または「住民税申告」をしている人 |
| ・児童扶養手当などの公的手当を受給しており、所得が低い人(自治体が把握している) |
✅ 結論:前年の収入が少なくて、確定申告や住民税申告がされていれば、基本的には自動で非課税に判定されます。
● 申請が必要になるケース
一方、次のような場合は、自治体に申告・申請をしないと非課税にならない可能性があります。
| 申請が必要な場合の例 |
|---|
| ・収入がなかった人(申告しないと“無収入”が把握されない) |
| ・会社を退職後、収入が減ったが申告していない |
| ・パートやアルバイトの収入があるが、確定申告・住民税申告をしていない |
| ・引越してきたばかりで、自治体に情報が引き継がれていない |
✅ 結論:「収入がない」人こそ、住民税の非課税判定を受けるために、住民税申告を行う必要があるのです。
💡 ワンポイント:収入がない人ほど「住民税申告」が重要
たとえ無職や専業主婦(夫)であっても、「私は収入がありません」と自治体に届け出ないと、非課税にならないケースがあります。
これを「住民税申告」と呼び、最寄りの市区町村役場で無料で行えます。
📌 住民税非課税になると、次のような支援が受けられる可能性があります
- 給付金(例:臨時特別給付金など)
- 医療費助成・保育料の減免
- 高校の授業料無償化
- 国保の減免
医療費助成や学費の補助にも影響あり
住民税の非課税世帯であることは、他の支援制度に影響を与える可能性があります。こども家庭庁の支援策として
・乳幼児医療費助成制度の対象拡大
・ひとり親家庭等医療費助成制度の利用促進
といった医療支援の拡充が図られています。また、教育支援の充実として幼児教育の無償化や大学進学支援の強化も進められています。これらの制度は、ひとり親家庭を支援する重要な要素です。
補足
これらの制度の適用条件や申請手続きについては、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
児童手当の有効な使い方
児童手当は、子どもの健やかな成長を支援するために支給される手当です。
通帳分けの実例、教育費への活用法
提供された資料には児童手当を「通帳分け」する具体的な実例は記載されていません。しかし、ひとり親家庭での子どもの金銭リテラシーを育む方法として、「節約=我慢」ではなく「賢い選択=より大切なことのための工夫」というポジティブなメッセージを伝えることが重要だとされています。これは、児童手当を教育費に活用する際の考え方にも応用できるでしょう。
また、子どもに比較購買力を育てるために、スーパーマーケットで商品の単価計算を教える「買い物探偵」という実践活動が推奨されています。これにより、衝動買いを避け、賢い消費者になるための基礎が身につきます。さらに、「価値選択」の対話を通じて、何が本当に重要かを子どもに考えさせる習慣を身につけさせることも重要です。例えば、「今はそれを買う計画はないけど、一緒に将来のためにどうやって貯金するか考えてみよう」といったフレーズは、長期的な計画と目標設定の価値を教えるのに役立ちます。
使わないと貯まる額(月15,000円×12ヶ月×18年=324万円)
この金額は、児童手当を毎月15,000円として18年間貯蓄した場合の計算例であり、提供された資料にはこの計算結果は記載されていません。 児童手当の実際の支給額は子どもの年齢や人数によって異なりますが、計画的に貯蓄することで、子どもの将来の教育費などに役立てられる可能性があります。
他にもある!自治体独自の支援
国が提供する制度の他に、各自治体が独自に実施している支援策も多数存在します。
家賃補助、学用品費補助など
こども家庭庁の「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」では、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭に対し、住宅支援として最大12か月間、家賃の実費を月額4万円を上限に支援しています。
また、多くの自治体で養育費の取り決めや確保のための支援が実施されています。これには、以下の費用に対する補助金が含まれます:
- 公正証書作成費用: 公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本等取得費用、郵便切手代などが補助対象となり、上限は3万円から15万円程度まで様々です。
- 養育費保証契約費用: 養育費の未払いに備え、保証会社と養育費保証契約を締結する際の初回保証料が補助される制度もあり、上限は5万円程度が一般的です。
- 強制執行申立費用: 未払い養育費の回収のため、裁判所への強制執行申立費用や弁護士費用が補助される場合もあります。
- ADR(裁判外紛争解決手続)利用支援: 弁護士会や認証ADR事業者が実施するADRの利用料が助成されることもあります。
また、多くの自治体で、離婚を考えている方や離婚協議中の方、ひとり親家庭の親を対象とした弁護士による無料法律相談が提供されており、養育費の取り決めや強制執行、親権、面会交流、慰謝料、財産分与など、離婚に関わる様々な法律問題に対応しています。
お住まいの市区町村の情報収集方法を紹介
これらの各支援制度の詳細は、こども家庭庁のウェブサイトまたは電話でも確認できます。 また、各自治体には母子・父子自立支援員が配置されており、ひとり親家庭の自立を支援するために、関係機関や社会資源とのネットワークを構築し、相談者の話を聞き、支援を行う役割を担っています。お住まいの市区町村のひとり親家庭就業・自立支援センター、母子・父子福祉センター、またはひとり親家庭支援センターなどの窓口に直接問い合わせることで、地域独自の支援制度に関する最新情報を得ることができます。例えば、仙台市では養育費等専門相談や同行支援も行われています。