目次
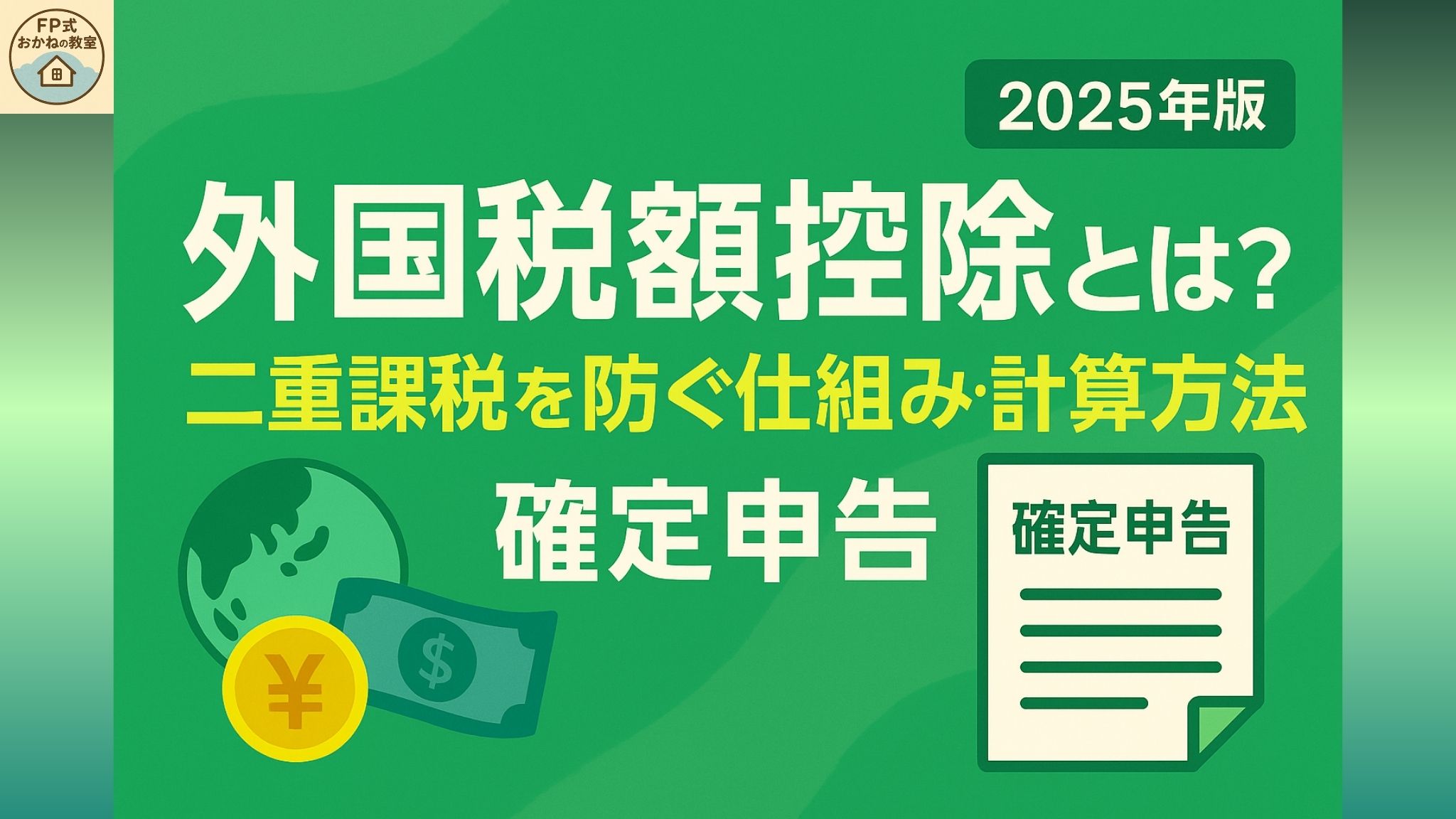
海外株や海外の投資信託に投資して配当金を受け取ったり、海外で働いて収入を得たりするとき、私たちは「二重課税」という問題に直面することがあります。
つまり、同じ所得に対して 日本と外国の両方で税金がかかる という不公平な状況です。これを防ぐために設けられている制度が 「外国税額控除」 です。
この制度を正しく理解すれば、払いすぎた税金を取り戻すことができ、結果的に投資や労働から得られる手取りを増やすことにつながります。
外国税額控除が必要な理由
なぜ二重課税が起きるのでしょうか?
- 日本の課税ルール(居住地国課税)
日本に住んでいる人は、国内で稼いだ所得も海外で稼いだ所得も、すべて日本で申告して税金を払う必要があります。 - 外国の課税ルール(源泉地課税)
一方で、所得が発生した国では、その国の法律に基づいて税金を取ります。
この2つのルールがぶつかることで、同じ収入に二重に税金がかかってしまうのです。
例えば、アメリカ株の配当金を受け取るとき、アメリカで10%課税され、日本でも20.315%課税される……といった状況です。
こうした不公平を調整するために、日本の税金から外国で払った分を差し引ける仕組みが外国税額控除です。
最新情報(2025年税制改正と住民税の変更)
- 2025年度税制改正
大企業向けの外国子会社合算税制(CFC税制)の見直しが行われましたが、個人の外国税額控除の基本的な仕組みに大きな変更はありません。 - 2024年度の住民税改正(重要)
これまでは「所得税は総合課税、住民税は申告不要」といったように、課税方法を分けて選ぶことが可能でした。
しかし2024年度からは 所得税と住民税を同じ課税方式で申告する必要があり、住民税で“申告不要”が選べなくなりました。
外国税額控除を利用する人にとっては、住民税の扱いにも注意が必要です。
制度の仕組み:どれくらい控除できる?
外国税額控除は、支払った外国税額を「日本の税金から差し引く」仕組みですが、差し引ける額には限度があります。
控除の流れ
- 所得税から差し引き
日本で支払うべき所得税から、外国税額を差し引きます。
ただし「控除限度額」があり、無制限ではありません。 計算式:控除限度額 = 日本の所得税額 × (外国所得 ÷ 総所得)→ 外国での所得の割合が大きいほど、控除できる額も大きくなります。 - 復興特別所得税から差し引き
所得税で引ききれない場合は、復興特別所得税から差し引けます。 - 住民税から差し引き
さらに余った場合は、住民税から控除できます。- 都道府県民税:12%
- 市町村民税:18%
- (政令指定都市は6%+24%で合計30%)
繰越控除制度
もしその年に控除しきれなかった場合は、翌年以降3年間に繰り越して調整できる仕組みもあります。
対象となる外国税金
控除の対象になるもの
- 個人の所得に対して課される税金(配当・利子・給与など)
- 所得の代わりに収入を基準として課される税金
- その所得に付随する附加税
対象外となるもの
- 延滞税や加算税などの罰金的な税金
- 自分の意思で還付や猶予を選べる税金
- 資本取引(出資金払い戻しなど)に課される税金
- 租税条約で対象外とされた税金
- NISA口座で受け取った配当の外国源泉税(NISAは日本では非課税のため)
申請方法と必要書類
外国税額控除を受けるには 確定申告が必須 です。申告不要制度を選ぶと適用できません。
申告時期と方法
- 通常の確定申告:翌年2月中旬〜3月中旬
- 還付申告:翌年1月から5年間さかのぼって可能
- 提出方法:税務署へ持参・郵送・e-Tax
必要書類
- 確定申告書
- 外国税額控除に関する明細書
- 証券会社が発行する「特定口座年間取引報告書」や「配当支払通知書」
- 外国税の証明書(税額・国名・配当金額などが分かる書類)
- 為替レートの記録(円換算のため)
実際の流れ
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、外国税額控除に対応した入力欄があり、自動で計算してくれます。複雑な計算を自分で行う必要はありません。
注意点
- 社会保険料や扶養判定に影響
配当金などを申告すると、健康保険料が上がったり扶養控除が外れる可能性があります。 - 繰越控除を忘れない
3年間の繰越ができるため、初年度で使い切れなくても翌年以降に利用できます。 - 専門家に相談
外国株投資や海外所得は複雑なため、迷ったら税務署や税理士に相談するのが安全です。
まとめ
外国税額控除は、海外で得た所得に二重に税金がかからないようにするための大切な仕組みです。
- 外国で払った税金を日本の所得税・住民税から控除できる
- 申告不要制度では使えないので必ず確定申告が必要
- 控除限度額や繰越制度があるので、計算は「作成コーナー」を活用すると便利
まるで外国で買い物したときに払った消費税を、日本の税金から引いてもらうような感覚です。
海外投資や海外収入がある人にとって、手取りを守るために欠かせない制度といえるでしょう。
