目次
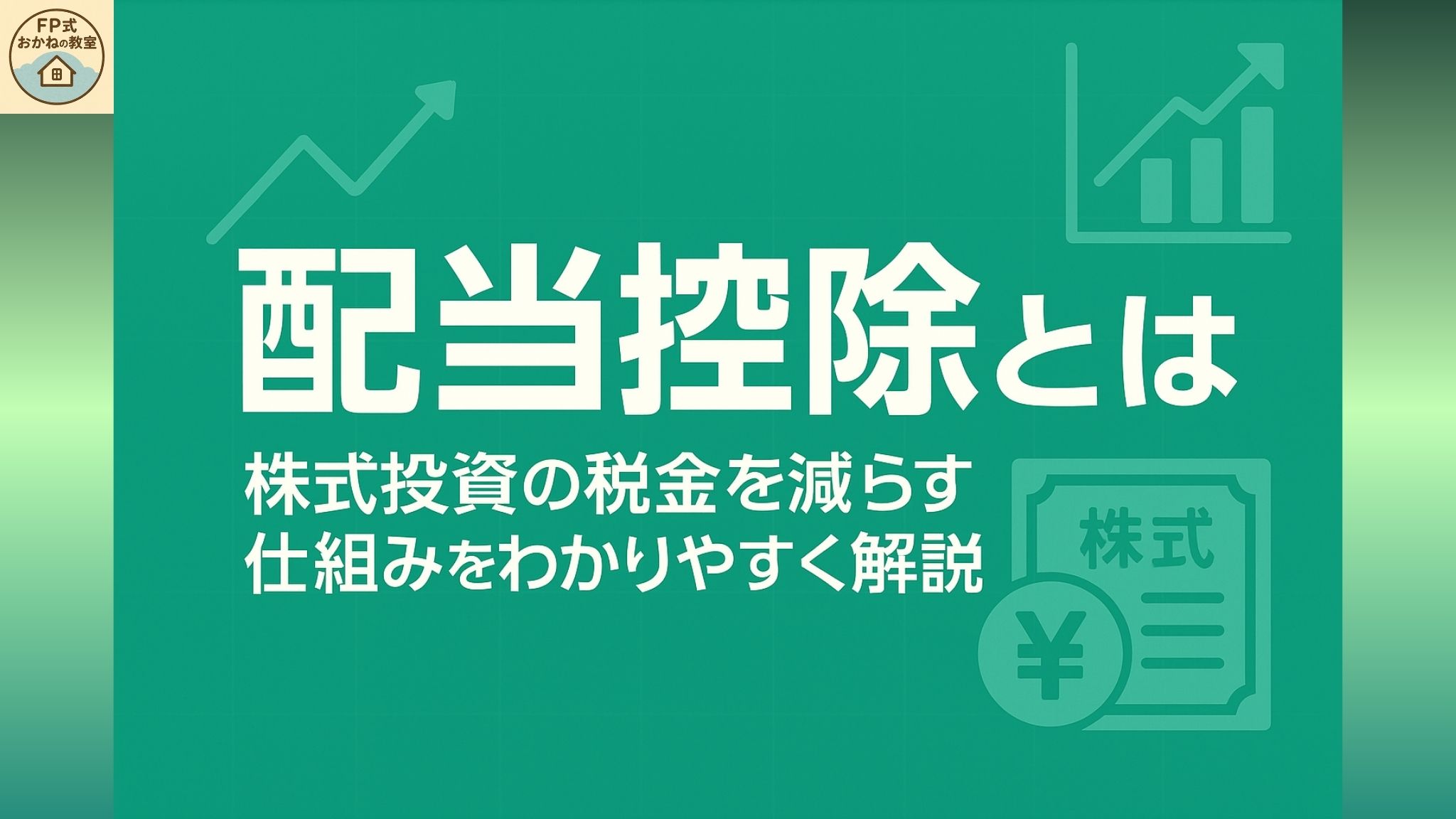
株式投資で得られる「配当金」は、働かなくてもお金が入ってくる魅力的な収入源です。しかし、この配当金には必ず税金がかかります。せっかくの収益が税金で削られてしまうと、「もっと手取りを増やしたい」と思うのは自然なことです。そこで注目すべき制度が 「配当控除」 です。この制度をうまく活用すると、配当金にかかる税金を減らし、最終的に受け取る金額を増やすことができます。この記事では、配当控除の仕組みや計算方法、使い方の流れまでをやさしく解説していきます。
配当控除とは?なぜ存在するのか?
配当控除とは、国内の株式配当金にかかる税金を軽くする制度です。
なぜこんな仕組みがあるのかというと、「二重課税」を防ぐためです。
- 企業が利益を出すと、まず法人税を払います。
- 残った利益の一部が株主に配当金として支払われます。
- その配当金を受け取ると、さらに所得税や住民税がかかります。
つまり「企業利益」に法人税と所得税の二重の税金がかかってしまうのです。これでは株主が不利になりますよね。
そこで国は「配当控除」を設け、二重課税を軽くする仕組みを作っています。投資を促し、株主への還元を後押しする目的もあります。
配当金の税金はどう計算される?3つの納税方法
上場株式の配当金を受け取るとき、基本は 源泉徴収(自動で税金が差し引かれる仕組み) です。
差し引かれる税率は 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)。
ただし、実際の納税方法は3種類あり、自分で選ぶことができます。
① 申告不要制度(そのまま完結)
証券会社から配当金を受け取るときに自動で税金が引かれ、それで納税完了。確定申告は不要です。
→ 一番シンプルな方法。多くの人が選んでいます。
② 総合課税制度(他の所得と合算)
給与などと合算して確定申告する方法です。
配当控除を使えるのはこの総合課税を選んだときだけ。
③ 申告分離課税制度(配当を独立して申告)
配当金だけを切り離して申告する方法です。株の売却損と配当を相殺する「損益通算」や「損失の繰越控除」が使えます。
→ ただし、配当控除は使えません。
配当控除でどれくらい得になる?
配当控除が特に有利なのは、所得が低~中程度の人です。日本の所得税は「累進課税」で、所得が多いほど税率が高くなります。
源泉徴収の税率は15.315%ですが、もしあなたの本来の所得税率がそれ以下なら、配当控除を使うと還付(払いすぎた税金が戻る)を受けられる可能性があります。
所得別のイメージ
- 課税総所得 330万円以下 → 配当金にかかる所得税が実質0%
- 330万円超~695万円以下 → 実質10%
- 695万円超~900万円以下 → 実質13%
計算例
年間30万円の配当金を受け取った場合:
- 本来の源泉徴収:4.5万円(15%)
- 配当控除(10%):3万円
- 実質負担:1.5万円
すでに4.5万円が引かれているので、確定申告をすれば差額3万円が還付され、手取りが増えるという流れです。
住民税の取り扱い
ポイントは、所得税と住民税で別の扱いができること。
例えば、所得税では総合課税にして配当控除を使い、住民税は申告不要(5%のまま)にする。
この方法を選ぶと、配当控除のメリットを取りつつ、住民税で不利にならずに済みます。自治体によって手続き方法が違うため、確認しておきましょう。
配当控除が使えないケース
すべての配当に配当控除が使えるわけではありません。
- 外国株の配当金 → 日本の法人税を払っていないため対象外
- J-REITの分配金 → 法人税が免除される仕組みがあるため対象外
- 所得が900万円超の人 → 総合課税にすると逆に負担が増えることがある
- 他の控除への影響 → 所得が増えた扱いになり、配偶者控除などが受けられなくなる場合
配当控除以外に税金を減らす方法
配当控除以外にも、配当金にかかる税金を減らす制度があります。
- NISA(少額投資非課税制度)
NISA口座での配当金は非課税。将来の資産形成に直結します。 - 損益通算と損失繰越控除
株の売却損と配当を相殺したり、損失を3年間繰り越すことで税金を軽くできます。
これらは配当控除と排他的になるケースもあるため、状況に応じて選択する必要があります。
配当控除を使う手続きの流れ
- 証券会社で「株式数比例配分方式」を設定(口座で受け取る方法)
- 確定申告書を作成し「総合課税」を選ぶ
- 住民税は「申告不要」を選べば税負担を抑えられるケースも
配当金の受取方法は配当基準日前に設定が必要です。金融機関のマイページで確認できます。
まとめ
配当控除は、国内株式の配当金にかかる税金を軽くしてくれる便利な制度です。特に所得が900万円以下の人にとっては、配当金の手取りを増やすチャンスになります。ただし「総合課税を選ぶ必要がある」「他の控除に影響することがある」など注意点もあります。NISAや損益通算といった別の方法とも比較し、自分にとって最も有利な方法を選ぶことが大切です。
賢く制度を利用して、株式投資のリターンを最大化していきましょう。
