目次
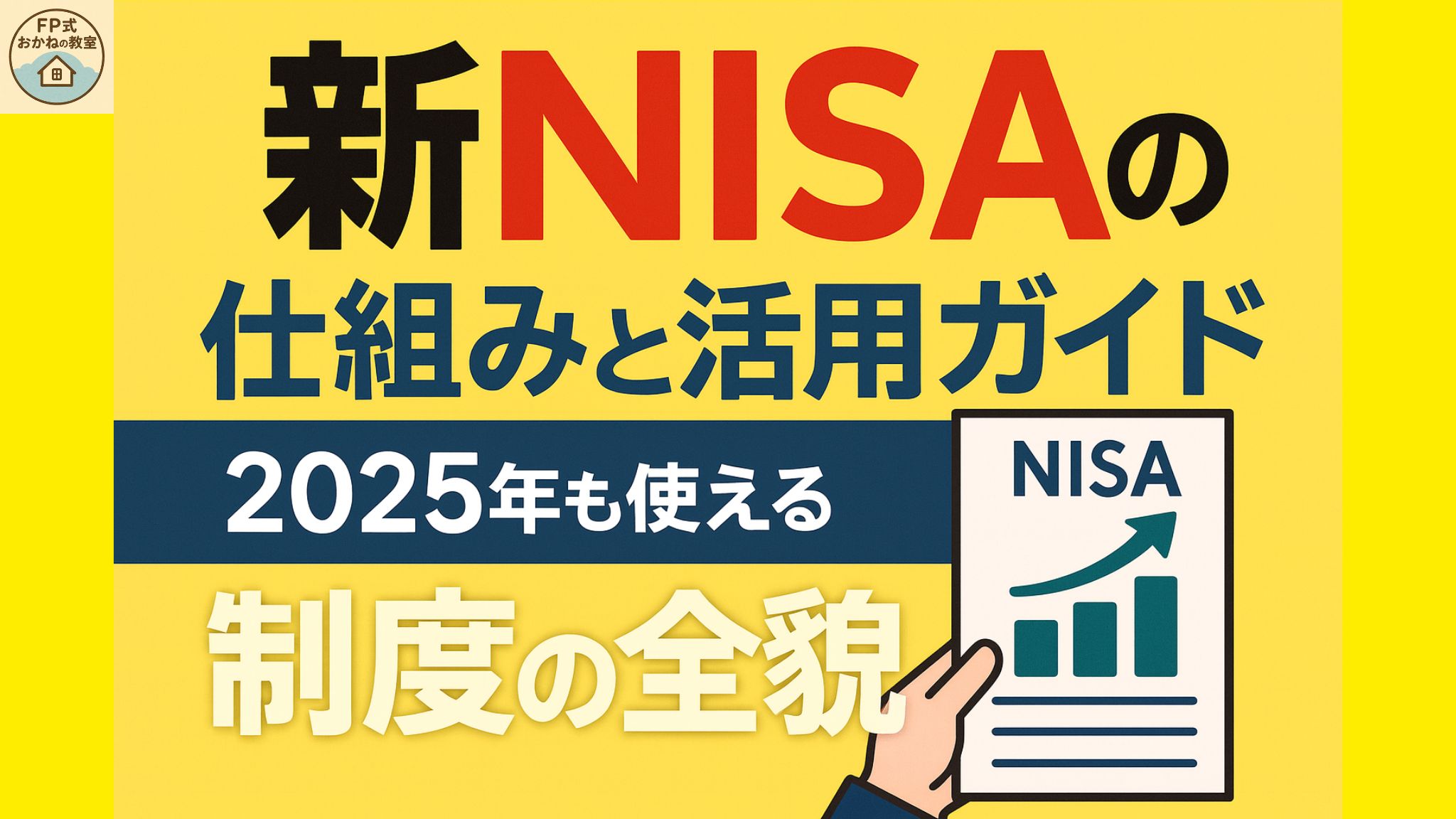
はじめに
新NISAは2024年1月にスタートした制度で、2025年も制度内容に大きな変更はありません。
しかし、開始から1年が経過し、口座数や投資額、利用者の行動傾向など最新のデータが明らかになっています。
本記事では、新NISAの基本的な仕組みから、2025年時点での最新の利用状況や活用ポイントまでを、初心者でも分かりやすく解説します。
NISAとは何か?その由来と目的
NISAとは、「Nippon Individual Savings Account」の略で、イギリスの「ISA(Individual Savings Account)」を参考に導入された制度です。
頭文字の「N」は日本(Nippon)を表しており、日本版ISAとして2014年1月に制度がスタートしました。イギリスのISAは、居住者の資産形成を促すための非課税制度で、株式型・預金型など複数のタイプがあります。日本版NISAも同様に、一定額までの投資で得た利益や配当が非課税となり、国民の資産形成を支援することを目的としています。
NISAのメリットは?
- 税制優遇: 通常、株式や投資信託から得られる利益や配当には約20%の税金がかかります。しかし、NISA口座で保有する金融商品については、一定期間、この税金がかかりません。つまり、税金を気にせず、利益をそのまま資産として増やすことができるんです。
- 少額投資: 少額から投資を始めることができるため、大きなリスクを背負うことなく、投資の世界に足を踏み入れることが可能です。
新NISAの主な特徴(2025年も継続)
2024年から始まった新NISAは、旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)の内容を統合・拡充した制度です。2025年も以下の特徴が継続しています。
つみたて投資枠と成長投資枠の併用
- つみたて投資枠:長期・分散・積立を目的とした投資信託等が対象(年間上限120万円)
- 成長投資枠:株式やETFなど幅広い商品が対象(年間上限240万円)
両方を併用することで、年間最大360万円まで非課税で投資できます。
年間360万円の非課税投資枠
合計で年間360万円の投資額が非課税となります(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)。
※2025年も上限額に変更はありません。
非課税期間・口座開設期間の恒久化
非課税で保有できる期間や口座開設可能期間が無期限化され、いつでも口座開設・運用が可能になりました。
非課税保有限度額1,800万円
非課税で保有できる総額は1,800万円まで。そのうち成長投資枠で保有できるのは最大1,200万円までです。
売却枠の再利用
保有資産を売却すると、その分の非課税枠を翌年以降に再利用可能。
これにより、資産の組み替えが柔軟に行えます。
※売却時の非課税投資枠の再利用について※
例を挙げると、あなたが積立投資で500万円を投資した場合、非課税枠の残りは1,300万円となります。この時、元本の100万円分を売却すると、次年度からはその売却分に相当する非課税枠が再度利用可能となり、非課税枠の上限が1,400万円に拡大します。
従来の制度では、一度売却した場合、その非課税枠を失ってしまい、再利用はできませんでした。しかし、新NISAの導入により、このような制限が撤廃され、投資者は自らのポートフォリオをより効率的に調整することが可能になります。この新たな柔軟性は、特に資産の再配分を頻繁に行いたい投資者にとって、大きな利点となるでしょう。
| 項目 | 旧NISA | 新NISA |
|---|---|---|
| 制度(枠)内容 | 「つみたてNISA」 「一般NISA」 「ジュニアNISA」 それぞれの併用は不可 | 「つみたて投資枠」 「成長投資枠」 という2つの枠で併用が可 |
| 口座開設期間 | 現在は開設不可 | 恒久化 |
| 非課税で運用できる期間 (非課税期間) | 一般NISA:最大5年間 つみたてNISA:最大20年間 | 無期限化 |
| 年間投資枠 | 一般NISA:120万円 つみたてNISA:40万円 | 成長投資枠:240万円 つみたて投資枠:120万円 ※2つの枠で併用が可 最大で360万円 |
| 非課税保有限度額 | 一般NISA 年間120万円×5年間=600万円 つみたてNISA 年間40万円×20年間=800万円 | 1,800万円 ※成長投資枠の上限あり 1,200万円まで |
2025年の利用状況と注目ポイント
2025年初頭、金融庁の発表によるとNISA口座数は約1,100万件を突破し、累計投資額は10兆円超に達しました。
特に人気なのは、長期分散投資に適した「全世界株式インデックスファンド」や「S&P500連動型ETF」です。一方で、成長投資枠の商品数が増えたことで「選択肢が多すぎて迷う」という声も多く、商品の選び方や運用方針に関する情報ニーズは依然として高い状況です。
新NISAの利用方法(2025年版)
1. 目標の設定
長期的な資産形成を目指し、自分がどのくらいの期間でどれだけ資産を増やしたいのかを明確にします。
例:「20年後に教育資金として500万円貯める」など。
2. 口座の開設
証券会社や銀行など、新NISA口座を提供する金融機関を選びます。
2025年時点では、主要ネット証券のほぼ全社が新NISAに対応。取扱商品数や手数料、アプリの使いやすさも比較しましょう。
3. 商品選択
- つみたて投資枠:低コストインデックスファンドが主流(例:全世界株式、S&P500)
- 成長投資枠:個別株やETF、REITなど幅広い商品が選べます
2025年は成長投資枠の対象ETFやREITが拡大し、選択肢が増えています。
4. 投資開始
定期的な積立や一括投資を行い、長期的な視点で運用します。
相場の変動に一喜一憂せず、計画に沿って継続することが大切です。
注意点(2025年版)
- 投資対象の制限
成長投資枠でもすべての商品が対象ではありません。投資信託の場合、金融庁が指定する基準を満たした商品に限られます。必ず金融機関のリストで確認しましょう。 - ロールオーバー不可
旧NISA(2023年まで)の運用分は新NISAに移管できません。非課税期間終了時には売却や課税口座への移行が必要です。
柔軟性の裏にあるリスク(意外なデメリット)
1. 判断の機会が増える
売却枠の再利用や複数枠の併用により、運用方針やタイミングを決める場面が増えます。投資経験が浅いと迷いやすく、機会損失や感情的な売買につながる恐れがあります。
2. 元本割れリスクは変わらない
非課税だからといって損失が出ないわけではありません。2025年は為替や海外市場の影響で値動きが大きくなる可能性もあります。長期分散投資や資産配分の見直しが重要です。
まとめ
新NISAは2025年も制度内容は変わらず、非課税枠の大きさと制度の恒久化が魅力の制度です。利用者数や投資額は順調に増加しており、国民の資産形成制度として定着しつつあります。一方で、投資対象や運用方針の選択は個人の責任で行う必要があり、情報収集と計画的な運用が欠かせません。
次は「NISAとiDeCoの違いと使い分け」を読んで、自分に合った資産形成戦略を立てましょう。
▼NISAとiDeCoの違いはこちら

